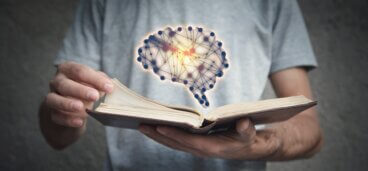興味深いアイディア…「デス・カフェ」とは?

ハリウッド映画を見ると、死は何度出てくるでしょう?一度に多くの人が死んだり、主人公がそれについて自慢げに語るシーンさえあります。一方で、現実の世界で死について話したいと思った時、周りの多くが黙ってしまいます。この話題で、アルゼンチンの精神科医がインターネット上にあるコメントを出しました。愛する人を失くした痛みを乗り越えられない患者が増えてきていると言うものです。喪失について話したいとき、聴いてくれる人をたよって、医者にたどり着く人が今日、たくさんいます。
「死を思いながら眠りにつき、人生の短さを思い目が覚める」
-ことわざ-
心地よいものではありませんが、死のような現実について話そうという気持ちや場所はあまりないものです。多くの人がその痛みを一人で乗り越えるしかありません。話そうとすると、人にあまり考えないようにと言われます。または、痛みから「目を背ける」ような方法を探します。
理にかなった、デス・カフェ
スイスの社会学者ベルナルド・クレタスが発案しました。1989年ジュネーブ大学の教授でした。「死の救済」という展示会を開いた際、多くの熱い思いのこもった反応を受けました。主に、多くの若者が死について語りたいという思いはあるが、どうしたらいいかわからないというものです。

そこで、2004年、クレタスは「救済カフェ」という集まりを開きます。死について自由に話す場所を設けるのが目的です。250人が参加しました。ウェルカム・アパタイザーが用意され、死に関する話は2時間以上続きました。意見交換が行われました。ルールはたった一つ、人の意見を尊重しあい、受け止めることです。このアイディアに興味を示す人は多く、他の場所でもすぐに開かれ、大成功でした。世界のあちこちで「デス・カフェ」が行われています。全大陸48カ国にわたり、4403もの団体があります。
なぜ死について語るのか?
多くの人が、意味もなく苦い話題を持ち出し、死について語る必要はないと考えています。これは、真の意味や恐怖や不安の表現を避け、正面から向き合いたくないという現れです。気持ちを隠しておくことを好むのです。死より現実的なものはありません。そして、避けられることではありません。人が皆たどる道であり、また、大切な人が暗闇に入っていくのを見ます。デス・カフェは死について語るというニーズを満たす場所です。

死について語る時、まず、ある種の不安が生まれます。それは、不慣れな領域の言葉を使うからです。この話題にオープンになり、恐怖と戦うことで、だんだん慣れていきます。病気を患う人や身近にそんな人がいる場合、死について語ることで、少し気が休まります。死という現実と向き合う強さや平和を与えてくれます。
イギリスの有名な心理学者エマ・ケニーはこのようにまとめています。「私達は、死は誰かのものだと自分から遠ざけて日々を過ごします。人生で難しいことの一つは、命のはかなさに気付くことです。」ここでの矛盾は、はかなさを知ることで、世界は広がり、命のもつ美しさが見えるようになるということです。私達の生活から死を取り除くと、死がもつ世界観を失うことになってしまうのです。

ハリウッド映画を見ると、死は何度出てくるでしょう?一度に多くの人が死んだり、主人公がそれについて自慢げに語るシーンさえあります。一方で、現実の世界で死について話したいと思った時、周りの多くが黙ってしまいます。この話題で、アルゼンチンの精神科医がインターネット上にあるコメントを出しました。愛する人を失くした痛みを乗り越えられない患者が増えてきていると言うものです。喪失について話したいとき、聴いてくれる人をたよって、医者にたどり着く人が今日、たくさんいます。
「死を思いながら眠りにつき、人生の短さを思い目が覚める」
-ことわざ-
心地よいものではありませんが、死のような現実について話そうという気持ちや場所はあまりないものです。多くの人がその痛みを一人で乗り越えるしかありません。話そうとすると、人にあまり考えないようにと言われます。または、痛みから「目を背ける」ような方法を探します。
理にかなった、デス・カフェ
スイスの社会学者ベルナルド・クレタスが発案しました。1989年ジュネーブ大学の教授でした。「死の救済」という展示会を開いた際、多くの熱い思いのこもった反応を受けました。主に、多くの若者が死について語りたいという思いはあるが、どうしたらいいかわからないというものです。

そこで、2004年、クレタスは「救済カフェ」という集まりを開きます。死について自由に話す場所を設けるのが目的です。250人が参加しました。ウェルカム・アパタイザーが用意され、死に関する話は2時間以上続きました。意見交換が行われました。ルールはたった一つ、人の意見を尊重しあい、受け止めることです。このアイディアに興味を示す人は多く、他の場所でもすぐに開かれ、大成功でした。世界のあちこちで「デス・カフェ」が行われています。全大陸48カ国にわたり、4403もの団体があります。
なぜ死について語るのか?
多くの人が、意味もなく苦い話題を持ち出し、死について語る必要はないと考えています。これは、真の意味や恐怖や不安の表現を避け、正面から向き合いたくないという現れです。気持ちを隠しておくことを好むのです。死より現実的なものはありません。そして、避けられることではありません。人が皆たどる道であり、また、大切な人が暗闇に入っていくのを見ます。デス・カフェは死について語るというニーズを満たす場所です。

死について語る時、まず、ある種の不安が生まれます。それは、不慣れな領域の言葉を使うからです。この話題にオープンになり、恐怖と戦うことで、だんだん慣れていきます。病気を患う人や身近にそんな人がいる場合、死について語ることで、少し気が休まります。死という現実と向き合う強さや平和を与えてくれます。
イギリスの有名な心理学者エマ・ケニーはこのようにまとめています。「私達は、死は誰かのものだと自分から遠ざけて日々を過ごします。人生で難しいことの一つは、命のはかなさに気付くことです。」ここでの矛盾は、はかなさを知ることで、世界は広がり、命のもつ美しさが見えるようになるということです。私達の生活から死を取り除くと、死がもつ世界観を失うことになってしまうのです。

このテキストは情報提供のみを目的としており、専門家との相談を代替するものではありません。疑問がある場合は、専門家に相談してください。